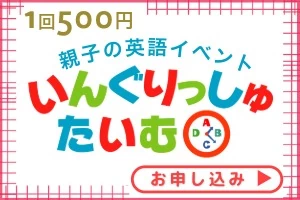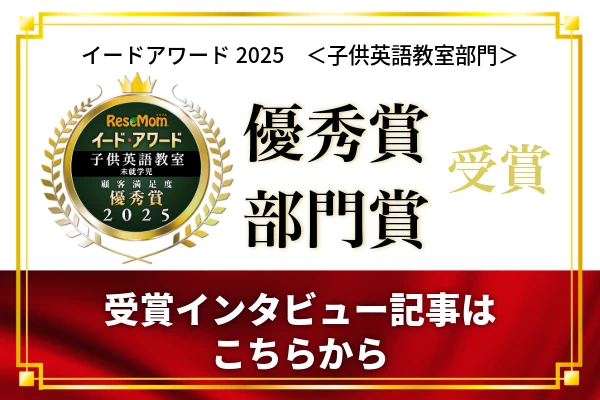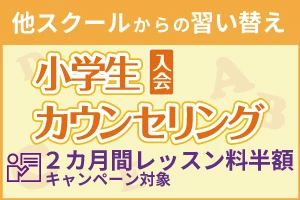「紙で読むこと」の良さとは?
公開日:2022年1月27日コラム
皆さんは普段、紙の本で読書しますか?
それともパソコンやタブレットなどの電子書籍リーダーで読書しますか?
ヤマハ英語教室のテキストは紙でできていて、手を使ってページをめくって学んでいますね。近年は学校教育にタブレットなどデジタル媒体が取り入れられることも増えてきました。デジタル機器は紙にとって代わる媒体なのでしょうか。そもそも紙で読む良さってなんでしょう?
今回は「紙」と「デジタル」それぞれが持つ読み書きの効果や使い分けについて、群馬大学の柴田先生にお話を聞いてきました。
 柴田博仁(しばた・ひろひと)さん
柴田博仁(しばた・ひろひと)さん
1968年秋田県生まれ。大阪大学大学院(数学)修了後、富士ゼロックス株式会社に入社。東京大学大学院工学修了(博士)。2020年から群馬大学情報学部教授。専門はコンピューター科学と認知科学。
人は文章を読むとき、「手で読んでいる」
紙のほうが読みやすく、目にやさしい。そう思っている人も少なくないと思いますが、本当にそうなのでしょうか。柴田先生は紙とデジタルの両方の媒体で「読む」「書く」のさまざまな実験をして、両者の違いを科学的に研究したり、デジタル教科書の効果について検証したりしています。
「紙はそれだけだとなんの機能もありませんね。できることは一つ、何かを描くことだけ。けれど紙はとてつもなくクリエイティブになれるんです。そんな紙の良さをコンピューターに応用したい。そんな目的から私の研究は始まりました」
柴田先生によれば、デジタルで読むことと、紙で読むことの最大の違いは「操作性、扱いやすさ」だと言います。「『読む』と一口に言ってもいろいろな行為があります。目で淡々と追って読む、指でなぞりながら読む、人と議論しながら読む、いくつもの資料を行き来しながら読むなど。そんなとき、紙とディスプレイとでは視覚的な影響の違いはほとんどありません。
けれどどうでしょう。ディスプレイの場合は、ページをめくったり、別のウィンドウに切り替えたりするときに、クリックしたり、メニュー画面からボタンを選んで押したりなど、いろいろな操作を意識的にしなくてはいけませんね。つまり読んでいる最中にプチプチと思考の中断が入って、負荷がかかっているんです。
一方で紙の本の場合、読んでいる途中で目次や注釈ページに移動したいとき、無意識に今読んでいるページに指を挟んでおきませんか? 誰に教えられたわけでもないのに、そこに戻ることを想定して手を使っているんです。紙を重ねたり、パラパラめくったり、指やペンをさしたり、書き込んだりなど、学習するときの『読み』は、いろいろな操作をしていますね。人は文章を読むとき、目で読むだけでなく『手で読んでいる』のだと言えます」
柴田先生はある実験を行いました。複数の図表とそれに関するテキストを相互に読み比べて、テキストの矛盾を指摘する校正テスト。実験者の半数は紙で、半数はパソコンのディスプレイで行いました。すると、校正スピード、矛盾点の検出率ともに紙を用いるほうが上回ったのです。
また、「書く」ことに関してもこんな実験結果があります。ある講義を聞いてメモを取り、あとで内容についてテストをします。実験者の半数は手書きでメモをとり、もう半数はパソコンで入力してメモをとりました。テストの結果、手書きでメモをとった側のほうが成績が良かったのです。なぜでしょうか。
「PCでは講師が言ったことをそのまま書き起こしているので、メモの量は多いですが、その内容は講師の発話そのものです。また、入力することに集中してしまい、思考がストップしてしまいます。
一方で手書きでは、講師が言っていないことを書いているという特徴がありました。講師が言ったことを解釈して、自分の言葉として置き換えているのです。さらに、タイピング操作のように負担がかからないため、考えながらメモすることができ、より脳の容量を使えるということがわかりました」
これらの実験は大人の場合であり、「読み」「書き」の学習段階にある子どもにとっては、もっと違いが顕著になるような研究結果もあるといいます。

より良い学習のために道具を使い分けよう
もちろんデジタル媒体にも利点はたくさんあります。音声や動画を再生して学べたり、オンライン授業ができたり、携帯するのも便利で、いつでもインターネットや電子辞書で調べ物ができます。こういった特徴は特に英語の学習において利便性が高いと思われます。けれど、健康への影響や、情報教育(ITリテラシーやセキュリティ)の必要性など懸念点もあります。中でもデジタル媒体における「学習効果」についてはどうなのでしょうか。
「子どもの場合はいくらデジタルに慣れても、紙の扱いやすさ(物理的操作)にとって代わるものではありません。また、デジタル機器は容易に検索ができますし、フィードバックが早く、何度もやり直せるという特徴があります。その反面、検索すれば答えがすぐに出てしまい、問題をじっくり考えるということがおろそかになったり、学習内容よりも機能やツールに夢中になったり、という懸念もあります。
紙で読む良さとしては、思考を妨げないこと。紙は扱いやすく、書きながら考えたり、話したりができます。学習するときはページを行き来することも、書き込みをすることも多いですよね。そうしたちょっとした操作性の良さの積み重ねが、学習効果に影響を与えます」
柴田先生はこうしたデジタルへの懸念点や紙の良さを挙げながらも、デジタルか、紙か、どちらか一方に偏らないほうが良いのでは、と考えます。
「デジタルも紙も道具ですから、より良い学習のために道具を使い分ける必要があります。見るだけ、聴くだけという場合はデジタル媒体を使うほうがいいと思います。ですが、子どもは道具に影響を受けやすいため、まずは思考を妨げず集中してじっくり考える習慣をつけるためにも、『手を使って読む』という紙の良さ、紙の本質を伝えることが大切ではないでしょうか」
柴田先生の英語学習方法を教えてください
私が英語を本格的にマスターしようと思ったのは30代の頃です。学習する時、とにかく声に出すことを中心にしました。車の中や、鏡の前でジェスチャーや声の抑揚を大げさにつけて、英語でするプレゼンの練習をしたりして。音声を聞いて、声に出して話すというやり方をしていると、おのずと読むことも速くなったんです。読解力がついて、英語で書かれたものを読むスピードが上がって、短時間でたくさん読めるようになりましたね。自分でも驚きました。もっと若い頃からやっておけばよかったと思っていますよ。
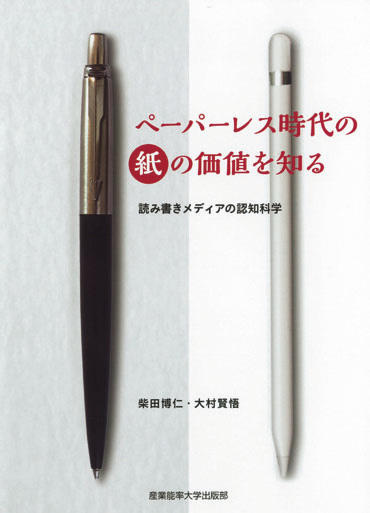 柴田先生の著書『ペーパーレス時代の紙の価値を知る読み書きメディアの認知科学』(柴田博仁・大村賢悟共著/産業能率大学出版部)。紙とデジタルを使ったさまざまな実験結果や考察が収められている。
柴田先生の著書『ペーパーレス時代の紙の価値を知る読み書きメディアの認知科学』(柴田博仁・大村賢悟共著/産業能率大学出版部)。紙とデジタルを使ったさまざまな実験結果や考察が収められている。
- 次の記事英語レッスン漫画/第1話『初めての習い事』
- 前の記事森泉さんインタビュー

 0120-055-808
0120-055-808